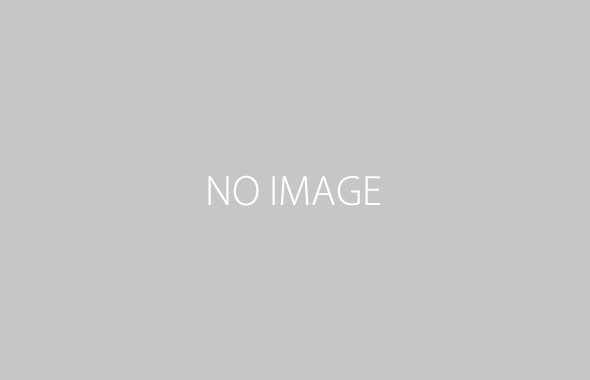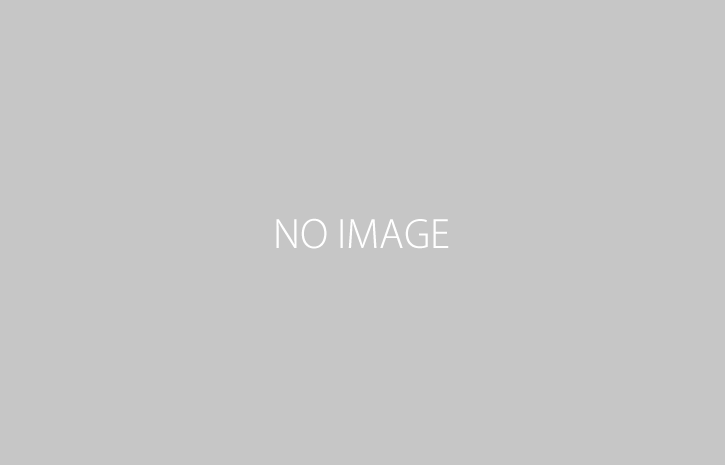
第19回 期待効用
情報経済論は、情報が不確実な場合に、経済主体がどのような意思決定や行動をとれば合理的であるのかを考えます。
原則として、情報の不確実性が高いほど、割り引いた計算をします。
たとえば、ある屋外のバザーで店を出すときに、天気のいい日には、これくらいの人々が集まるという過去のデータがあったとします。明日開催される場合に、翌日の天気予報が、雨と出ていれば、お客さんが少ないことが予想され、商品の材料も少なめに仕入れておこうという判断をします。これは、期待効用の計算を暗にしていたことになります。
期待効用理論(expected utility theory)とは、「行動の帰結が不確実な状況における合理的な経済主体の判断は、結果に関する効用の期待値にもとづいてなされる理論」(世界大百科事典)のことです。
ここで、期待値とは、「確率変数のすべての値に確率の重みをつけた加重平均のこと」といえます。
すなわち、n通りの結果Xk(k= 1,2,・・n)と、そのときに起きる確率Pk(k=1,2、・・n)の積和です。
式で表すと、
E = P1×X1 + P2×X2 + ・・+ Pk×Xk
となります。
ちょっと抽象的なので、以下のような簡単な事例を解きながら、もう少し考えてみます。
ある個人が、所得yから効用を得ていると考え、その効用関数は U=y0.5
とします。Uは、効用を表します。ここで、経済状況がいいときには、400を得られ、悪いときには100とします。また、経済状況のいい確率は、0.8で、悪い場合が、0.2とします。このときの個人の期待効用(EU)は、
EU = 0.8×4000.5 + 0.2×1000.5
= 16 + 2
= 18
この18という期待効用は、もし、100%景気がよいときは20なので、少しばかり割り引いた値となっていることが分かります。
ここでも、人間が合理人(経済人)であるという仮説に基づいています。実際の個人は、あまりこのような期待値計算が得意ではありません。それが、行動経済学が導く効用関数につながりますが、それは、またあとで議論します。