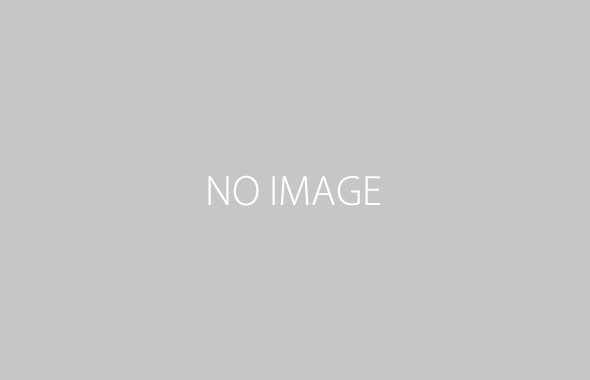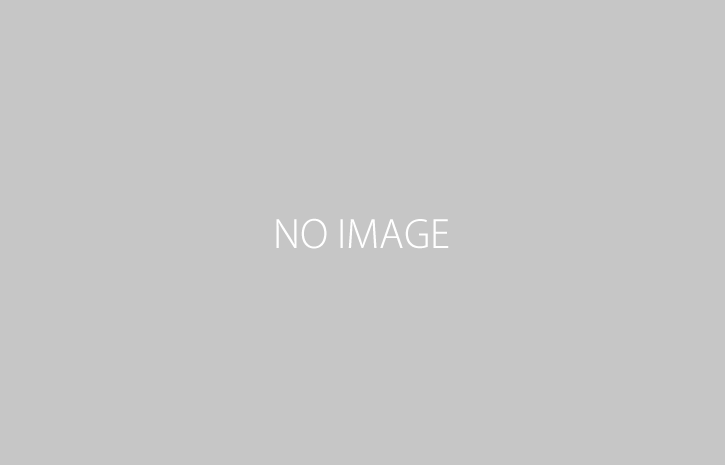
第62回 効用とその可測性
ここからは、「消費者の理論」を述べていきます。
そのはじめとして、「効用(utility)」概念を考えます。
効用とは、「個々の消費者が主観的に感ずる欲望満足の程度」(『経済学小辞典』、岩波書店)であると考えます。
財やサービスをお金を出して購入するのですから、その金額に見合った満足は重要です。
しかし、この効用概念がなかなか難しい概念である理由のひとつは、その「主観性」にあります。どの財に対してどの程度の満足感を得るのかは、個々人ごとに異なるでしょう。さらには、同じ人でも、条件によって異なるといえます。マーケティング理論の泰斗、P・コトラーの「ラテラルマーケティング」の理論を援用すると、財の効用は、「ニーズ」と「ターゲット」と「オケージョン(機会)」によるといいます。前2者は、固定するとしても、このオケージョンの中には、以下の4つの要因があるといいます。第一は「時間」であり、第二は「空間」であり、第三は「状況」であり、第四は「経験」です。たとえば、食べ物でも、いつ、どこで、どのような状況で、どう経験するかによって、その満足感は大いに異なるでしょう。その組み合わせは、無限通りといえるでしょう。
このひとつをとってみても、消費者の効用を特定することは簡単なことではないことが分かります。
とはいえ、経済学のもっとも基礎的な概念があやふやでは厳密な理論は構築できないので、効用に関して、いろいろな見方が提起されてきました。
その第一は、効用を「基数的効用(cardinal utility)」としてみるものです。効用の1は、あくまでも1であり、効用の2は、その2倍とみます。数値自体に意味があるとみます。しかし、本当に、主観的な満足感をそのように数値で把握できかつ表現することが望ましいのかが問われるようになりました。
そこで、第二は、効用を「序数的効用(ordinal utility)」と考えました。効用理論を展開するうえで、絶対的数値に意味はなく、その序列、順位こそ意味があるという見方です。現在の標準的なミクロ経済学は、この序数的効用概念を採用しているとみられています。これは、顕示された序列で効用理論は議論できるとみています。しかし、価格と個々人がもつ効用(限界効用)は、同じではありません。「余剰(surplus)」概念をみても、市場均衡価格が決まったからといって、その市場に参加した個々人の財に対する満足度は異なっています。余剰は、必ずしも顕示されていないのです。
そこで、基数的効用として、消費者の「支払意思額(WTP:Willing to Pay)」を表明してもらう手法も出てきています。そのひとつが、「CVM(仮想評価法)」です。この方法にもいろいろな難点がありますが、それは後日お話をするとして、消費者の効用ないしは満足度の金銭的表明ならば、効用は可測性があるといえます。
筆者のグループでは、この「効用の可測性(measurability of utility)」を実証するために、数万人以上のアンケート調査を実施しています。その可能性や限界は、またの機会にお話ししたいと思います。