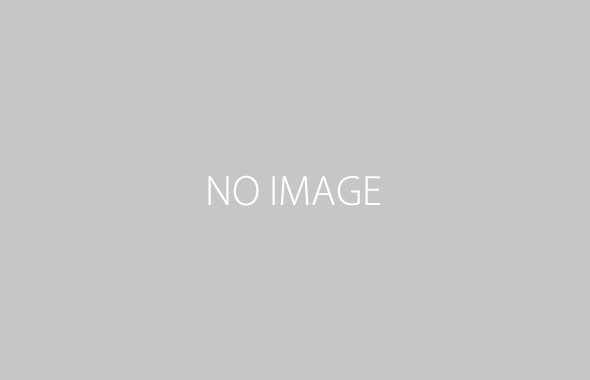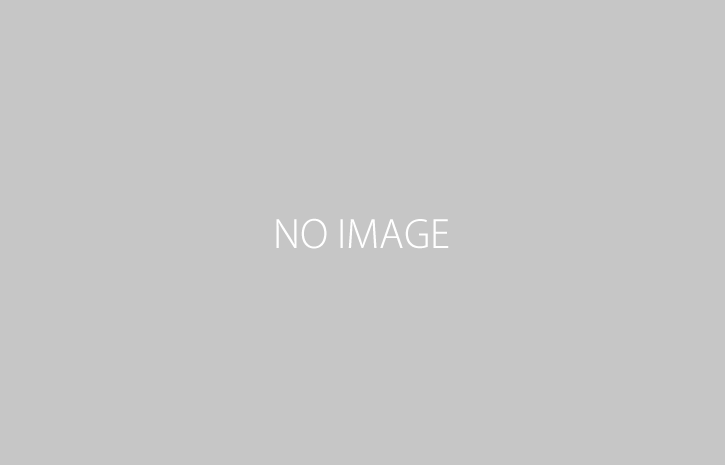
マクロ経済学第6回 相対所得仮説その1
相対所得仮説は、現在の所得以外の要因も、現在の消費に影響を与えるものと考える消費仮説です。
これは、J・デューゼンベリー(James Stemble Duesenberry;1918-2009)が提唱したもので、この相対所得仮説には、主に2つの考え方があります。
今回は、その1として、時間的相対所得仮説を考えます。
一個人においても、もっとも高い所得のときにはもっとも大きな消費をしてるということはありそうな話です。所得はいろいろな社会経済状況や個人的理由で、下がることもあります。しかし、一旦、高まった消費は急には下がらないという話もよく耳にします。
では、時間的相対所得仮説を定式化してみます。
C = cY + c1Y1 ・・・・・・①
C/Y = c + c1Y1/Y ・・・・・②
Y1 = Y・・・・・・・・・・・③
C/Y = c + c1 ・・・・・・・・④
C:消費 c:現在の限界消費性向 Y:現在の所得
c1:もっとも大きかった所得の時の限界消費性向
Y1:もっとも大きかった所得
第一式より、消費は、現在の消費ともっとも大きかったときの消費の要因から形成されるとみます。その両辺をYで割ると、第二式となります。この式より、短期的に、現在の所得が減少すると、平均消費性向は、上昇します。これに対して、長期的には、個人または社会経済の成長により現在の所得が最高の所得と同じになった場合が、第3式です。すると、第四式のように、平均消費性向は、右辺のそれぞれの限界消費性向は定数なので、一定となります。
ここで明らかとなったことは、所得が一時的に低下しても、消費に歯止めがかかるということです。これを、「ラチェット効果(ratchet effect)」といいます。景気の大きな落ち込みを防ぐ効果も期待できます。